看護実習でよくある悩みのひとつが、「指導者と教員の言っていることが違う!」という場面。
「どっちの指示を優先すればいいの?」と混乱してしまい、実習が怖くなる学生さんも少なくありません。
実はこれ、あなただけでなく多くの看護学生が経験している“あるある”なんです。
背景には「指導者は患者さんの個別性を大切にしている」「教員は看護の理論や一般知識を基に指導している」といった立場の違いがあります。
この記事では、なぜ指示の違いが生まれるのかを解説しつつ、実際に指導が食い違ったときの対処法や気持ちの整え方をご紹介します。
読んだあとには「もう怖くない!」と前向きに実習に臨めるはずですよ!
指導者と教員の指示が違う…実習でよくある悩み
「え、どっちを優先すればいいの?」学生の混乱
例えば、指導者からは「学生さんできるだけ患者さんと関わってね」と言われたのに、教員からは「病室に行くタイミングと頻度を考えて」と指示される…。
矛盾するように聞こえてしまい、どう動けばいいのか迷う瞬間ってありますよね。
実際にあった指示の違いの例
指導者
「術後は早期離床が合併症予防には重要だから、離床を促す看護をしていってね」
教員
「術後は疼痛や倦怠感があるから、安楽に過ごせるような看護を立案してね」
こうした場面に遭遇すると、「私のやり方が間違ってるの?」と不安になる学生も多いはずです。
なぜ指導者と教員で指示に違いが出るのか
指導者は患者さんの個別性を把握している
指導者は普段から患者さんのケアに直接関わっており、その人の生活背景や性格、体調の変化を細かく把握しています。各病院によっても、治療の過程が異なることもあります。
だからこそ、「今の患者さんにとって必要な看護」を一番理解している立場と言えます。
教員は教科書など一般的な知識を基に指導している
一方で教員は、学生に「基本的な看護過程の流れ」や「教科書にも記載される一般的な知識を活用できる力」を育てることを重視しています。学内で得た知識を、臨床の現場で活かせる知識にすることが教員の目的です。
そのため、実際の現場ではやや理想的に聞こえる指導が出てくることもあります。
両者の立場の違いを知ることが大切
つまり、指導者は「患者さんの個別性」、教員は「看護の一般的な理論」に基づいて学生にアドバイスしているんです。
どちらも学生にとっては大切な学びなので、矛盾しているように感じても「視点が違うだけ」と理解できると気持ちが楽になります。
指示が違うときにありがちな学生の反応
どちらにも合わせようとして混乱
両方の言うことを完璧にやろうとすると、頭も体もついていかず混乱してしまいます。先ほどお話した、両者の立場の違いを理解し、「こういう意見もあるんだな」と少し客観的に冷静にとらえてみてください。
どっちかを無視してしまうリスク
「もう分からない!」と投げ出したくなる気持ちはとてもよくわかります。
ですがどちらかの指示を軽視すると、信頼を失ってしまうことも…。現場で指導する指導者と、最終的に実習の合否を判定する教員。どちらかの意見を軽視してしまうことは、実習をクリアするためには避けなければなりません。
相談できずにストレスがたまるパターン
「質問したら怒られそう」と我慢してしまうと、不安やストレスがどんどん大きくなってしまいます。同じ実習メンバー同士で情報共有し、意見交換をしてみてもよいですね。同じように悩んでいるメンバーもいるはずです。
指導者と教員の言うことが違った時の対処法
メモを活用して混乱を避ける
その場で言われたことをしっかりメモして、後から振り返って整理することが重要です。振り返ったときに、「指導者さんと先生、なんか言ってたことが違う気がするけど・・・。」と曖昧にならないようにしましょう。
指示の違いを整理する
先ほどお話した、指導者と教員の立場の違いを把握したうえで、指導内容の違いを整理してみましょう。きっとどちらも間違ったことは言っていないはず。
実際にあった指示違いの例
指導者
「術後は早期離床が合併症予防には重要だから、離床を促す看護をしていってね」
教員
「術後は疼痛や倦怠感があるから、安楽に過ごせるような看護を立案してね」
指導者は、術後経過、合併症の有無、術後の指示、患者さんの痛みや苦痛の程度を把握したうえで、離床が必要であると判断しています。
一方教員は、術後の安静期間に、患者さんが苦痛を最小限にできるように看護を提供してね、と言っています。患者さんの詳細な情報やをもとにしたものではなく、一般的に術後は安静が必要で、痛みを伴う場合が多いのでこのような指導になります。
どちらも間違っていませんし、どちらも大切な視点です。でも、離床すればいいのか、安静にすればいいの、わかりませんよね。
私が実習指導者の立場としておすすめするのは、指導者の意見に、教員の意見を組み込むことです。
今回の例で言えば、指導者さんが指示する早期離床という看護に、教員の指示する痛みや苦痛を和らげる看護を組み込みます。
「患者さんの疼痛や苦痛の程度を確認し、必要に応じて疼痛コントロールを行いながら早期離床を進める」という目標にすれば、患者さんの苦痛にも着目しながら、早期離床という現場で今必要な看護が実施できますね。
教員・指導者に確認に確認してみる
そうは言っても、「やっぱりしっくりこない」という場合もありますよね。
そんなときは、自分なりに指導者と教員の指示を整理し、教員の先生に相談してみましょう。
できれば、先に教員の先生に相談することがおすすめです。教員も患者さんの情報が少ないうえで指導を行っていることは理解されているはずなので、タイムリーに現場で必要な看護が見えていない場合もあります。
教員の先生に、自分なりに整理した両者の指示を述べ、どちらも必要な視点に感じるがうまく看護に繋げられないので相談させてほしい、と話してみましょう。
実習中の混乱を最小限にする工夫
事前の情報共有・自己確認
実習開始前に患者さんの情報をしっかり確認しておくと、指導者と教員の指示の背景が理解しやすくなります。指導者さんと教員の先生で指導する視点・立場が違うことも合わせて確認しておきましょう。
周囲の学生との情報交換
同じように困っている学生も多いので、休憩中に「さっきこう言われたんだけど、どうしてる?」とシェアすると気持ちも楽になります。患者さんの個人情報になる場合もあるので、話す場所には注意してくださいね。
ポジティブに受け止めて学びに変える
「現場と一般知識・理論、両方を学べるのは学生の特権」と思えたら、少し気持ちも前向きになりまよ!それこそ両者をかけ合わせたらとっても良い看護になります。
まとめ
実習中に指導者と教員の言うことが違って戸惑ったり、悩んだり、多くの学生が同じ気持ちを経験しています。どっちが正しいのか迷うのも当たり前ですし、混乱することも決して悪いことではありません。
大事なのは、なぜ言っていることが違うのか、背景を考えながら、少しずつ整理して対応していくことです。そうしていくうちに、自分なりのやり方や自信も見えてきます。
焦らず、一歩ずつ前に進んでください。あなたは一人じゃないし、こうした経験も必ず成長につながります。
矛盾を感じる瞬間もありますが、それも含めて看護の奥深さ。10人いれば10通りの看護があります。
実習を通して「現場で活きる看護」を身につけていきましょう✨
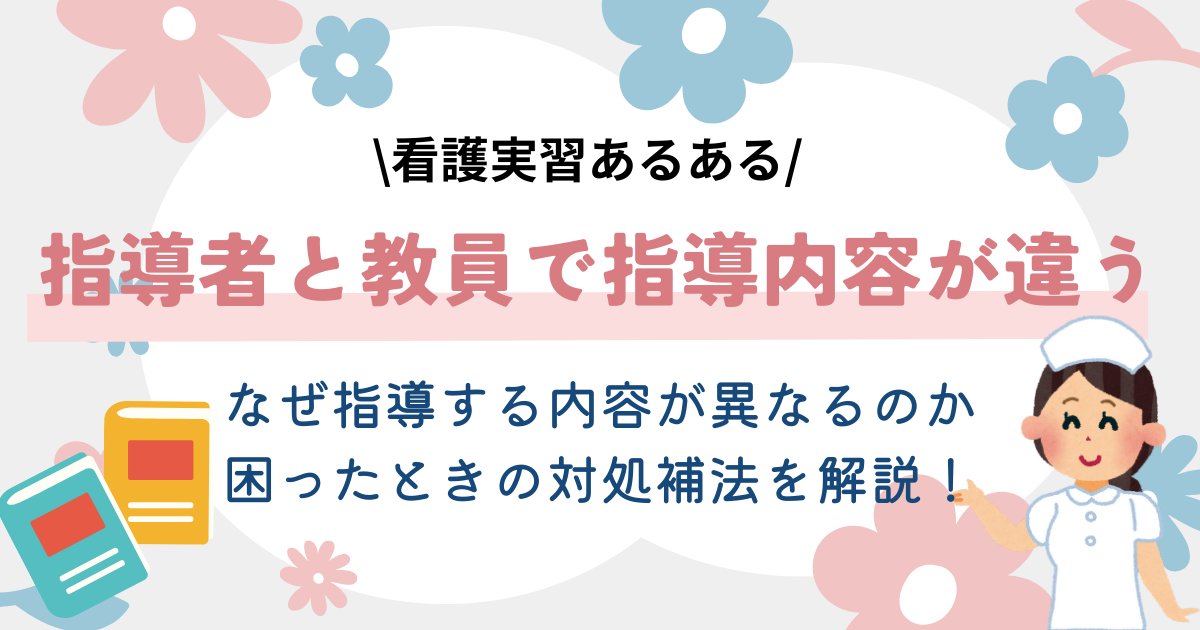
コメント