看護実習では「患者さんとのコミュニケーションが大切」とよく言われます。でも、実際に患者さんの前に立つと、どう声をかけていいのか分からなくなることもあります。今回は、私が1年生の基礎看護学実習Ⅱで経験した「発声が困難な患者さん」とのエピソードです。
看護実習中に患者さんとのコミュニケーションでつまずいた話
声が出せない患者さんとの出会い
担当したのは、気管切開をしカニューレを挿入していて声が出せない患者さんでした。
最初は私が「クローズドクエスチョン」で一方的に質問し、患者さんは頷くか首を振るだけ。一問一答のやり取りになり、病室には私の声だけが響いている状態でした。
その患者さんはとてもやさしく、私の問いかけに笑顔で反応してくださっていたのですが、私が用意していた質問を聞き終えると病室は静まり返ってしまいます。周りの学生は患者さんと病室や談話室で楽しそうにお話をさせてもらっているのに、私だけ・・・。
「会話になっていない、どうしたらいいんだろう?」
焦りと不安でいっぱいになりました。筆談も試してみましたが、患者さんから「書くのもしんどい」と言われ、さらに行き詰まりを感じました。
患者さんの気持ちに寄り添う
実習開始数日は、コミュニケーションがうまく取れない、会話にならない、病室で患者さんとどのように過ごせばいいのか、と自分のことで頭がいっぱいでした。
そんな時、患者さんが手振りと口パクで「声が出せたらね・・・」と伝えてくれました。
私はハッとして、「一番つらいのは声が出せない患者さん本人」だと気づかされました。そして、今までコミュニケーションが取れなくて悩んでいることが、とても小さいことに思えたんです。
“いま患者さんは何を望んでいるのか?”
“できるだけ患者さんに負担にならないコミュニケーションの方法は何か?”
患者さんの表情や仕草、病室の環境、生活リズム、呼吸困難感や痰の量にも注目しながら、少しでも意思疎通できる方法を考えました。そして主治医や看護師さんに相談し、スピーチバルブを導入してみることに。
声が出た瞬間の感動
スピーチバルブを装着し、最初は息苦しさがありましたが、呼吸方法を工夫したり装着時間を短くしたりして少しずつ練習しました。
そして、かすれた声ではありましたが、患者さんが言葉を発したのです。「声が出せるわ、ありがとう」
その瞬間、患者さんは涙を流して喜んでくださり、私も思わず胸がいっぱいになりました。
学んだこと
看護のコミュニケーションは、言葉だけではありません。
表情や仕草から患者さんの気持ちを汲み取ろうとする姿勢が大切だと実感しました。
この実習で担当させていただいた患者さんは、声を出したい、という思いが強くあったので、発声が可能になる方法を検討しましたが、それ以前に、患者さんの気持ちに寄り添うことが本当に大切だと感じました。
自ら患者さんの思いに寄り添うことで、患者さんとの信頼関係を築き、患者さんのニーズをとらえることで本当に必要な看護が見えてきます。”会話でのコミュニケーション”が重要なのではなく、そのコミュニケーションからいかに患者さんの思いを引き出し、看護につなげていくか、が重要だと学びました。
会話は情報を得るための手段の一つにすぎません。
このことのに気づかせてくれた患者さんには今でも本当に感謝しています。実習から十数年たちますが、時々ふと思い出します。そのくらい思い出深い実習でした。
患者さんとの関わりでつまずいた経験は、きっと誰にでもあると思います。大切なのは「失敗した」ではなく、「そこから何を学べるか、患者さんの思いに自分は気づけているのか」と考えることだと思います。
今回の体験を通して、改めて「コミュニケーションの奥深さ」を実感しました。前回の記事では、コミュニケーションに困ったときの対処法をまとめているので、実習での患者さんとの関わりのヒントになれば嬉しいです。
👉 患者さんと会話が続かない…看護実習でコミュニケーションに困ったときの対処法
最後まで読んでいただきありがとうございました🌸
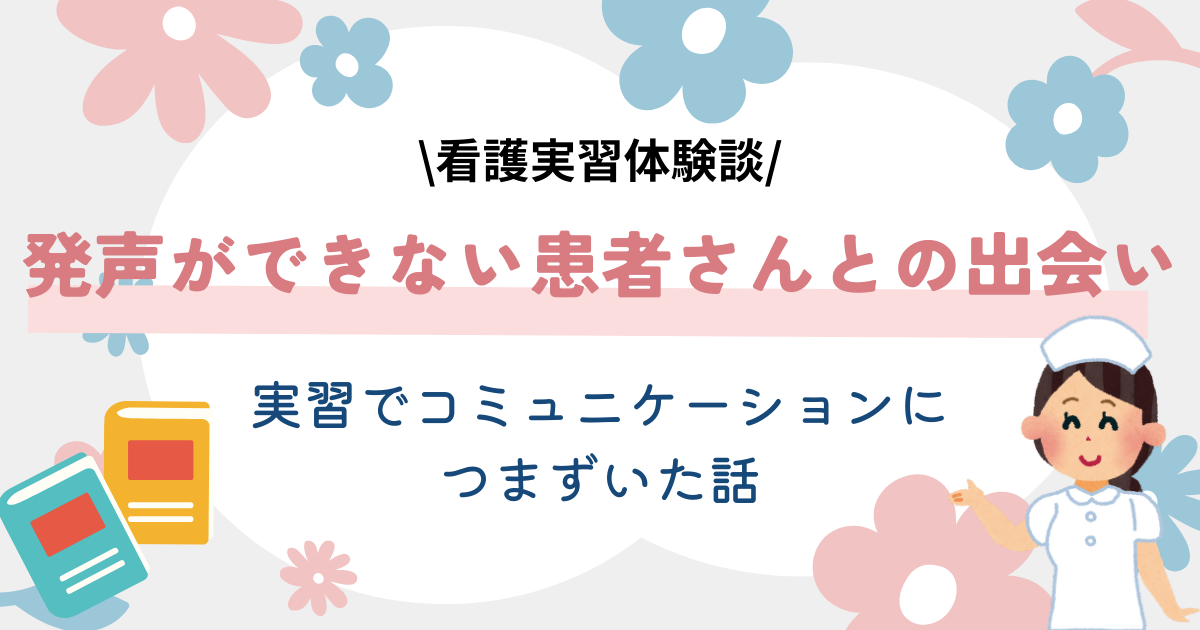
コメント