看護実習の中で多くの学生さんが苦手に感じる「カンファレンス」。
看護学生のみなさんの中にも、「何を話せばいいの?」「進め方が分からない」と不安に思っている方が多いのではないでしょうか。
私自身も学生の頃、カンファレンスの目的をよく理解できていなかったため、メンバーが一人ずつ意見を発表して終り。全員の発言が終わったあと沈黙が続き、指導者さんから「このカンファレンス意味あった?」とお叱りを受けた経験もあります。
今回はそんな失敗談を交えながら、看護学生が知っておきたい”カンファレンスの目的や進め方”、”テーマ設定のコツ”についてまとめてみます。
そもそもカンファレンスとは?
医療の現場におけるカンファレンスとは、患者さんに関わる複数の職種(医師、看護師、薬剤師、栄養士、リハビリ、心理カウンセラー、等)が、それぞれの立場から意見を出し合うことで、患者さんにより良い治療や看護を提供することが目的になります。
看護学生のカンファレンスも同様に、「ただ意見を発表する場」ではなく、患者さんへの看護をより良いものにするために、チームで考えを深める場です。
- 患者さんの情報を共有する
- 看護の方向性を確認する
- さまざまな視点から考えを広げる
この3つが大きな目的です。この目的を意識しながら自分の意見を発言し、メンバーの意見を受け入れられると良いですね。
カンファレンスに必要な事前準備
カンファレンスは、”事前準備が8割”と言っても過言ではないほど、準備が必須です。実習メンバーで十分にカンファレンスの準備を行っておくことで、本番でも活発な議論が展開され、有意義な時間になります。
役割を決めておく
看護実習でのカンファレンスでは、「司会進行役」「書記」「書記代理」を決めておきましょう。
司会進行は、時間管理をしながらカンファレンスを進め、参加するメンバーから満遍なく意見が出るように発言を促し、最後に出た意見をまとめるなどの役割があります。
書記は、カンファレンスで議論された内容や、決定事項、まとめなどを記録します。
書記代理は、書記を担当しているメンバーが発言している際に、記録を代理する人のことです。書記代理は絶対に必要な役割ではありませんが、カンファレンスが終わってから書記役の人が自分が発言を思い出しながら記載するのは大変なので、事前に決めておくと良いですよ。
カンファレンステーマを決める
基本的に毎日行われるカンファレンス。「明日のカンファのテーマ何にしよう・・・」と悩みますよね。思いつかないからと言って、なんとなくテーマ設定をしてしまうと、メンバーから意見が出ない、自分も何を発言していいかわからない、結果的に「このカンファレンスでの学びは何か」わからなくなってしまいます。
おすすめのカンファレンステーマの設定方法は、
実習で「困っていること」「失敗したこと」をそのまま議題にすることです。
例えば、患者さんとコミュニケーションがうまく取れずに、困っているメンバーがいるとします。そこで、カンファレンスの議題を「患者さんとコミュニケーションをとる方法について」とすると、問題解決に向けて、他のメンバーが自分の体験談であったり、コミュニケーションの工夫などを発言できます。
カンファレンスを行う目的を決める
カンファレンステーマが決定したら次に重要なことが、カンファレンスを行う目的を、決めておくことです。
さきほどの「患者さんとコミュニケーションをとる方法」で言うと、
A:「コミュニケーションが取れず、情報収集ができなくて、看護につなげられず困っている」
B:「患者さんが自分の思いを表出する場面が少なく、抱え込んでいるのではないかと心配している」
AとBは同じコミュニケーションに関する困りごとですが、解決したい内容が違えば当然議論の内容も異なります。このことをメンバー同士で共有しておくことが重要です。今回の例Aで言うと
カンファレンステーマ
「患者さんとコミュニケーションをとる方法について」
カンファレンスの目的
「コミュニケーションの中から必要な情報を収集し、患者ニーズに合わせた看護を実践するため」
このように設定することができますね。
議題の内容について予備知識をつけておく
さきほどの患者さんを例に挙げたカンファレンスの場合、患者さんに関する基本情報(年齢、性別、疾患名、受けている治療内容、生活背景等)を知っておく必要があります。そして、発達段階や疾患、治療内容に関しても勉強をしておきましょう。
発達段階がコミュニケーションに影響しているかもしれませんし、疾患や治療の内容によってはコミュニケーションに影響を及ぼすことだってあります。これらのことを知っておかなければ、まさに机上の空論で内容のない議論になってしまいますね。
カンファレンスの時間・場所を相談、報告する
カンファレンスは限られた時間の中で行うので、メンバーやスタッフが決められた時間・場所に集まらなければなりません。指導者さんと相談し、皆が集まれる時間とその時間に使用していい場所の確認をしておきましょう。
カンファレンスの進め方
挨拶・導入
「これからカンファレンスを開催します。よろしくお願いします」
「本日のカンファレンステーマは、○○〇、目的は△△△です」
情報のの共有(受け持ちのメンバーが発表)
「Aさん、70代男性、○○(疾患)で入院し、現在△△の治療を受けておられます。□□(困っている内容を具体的)について話し合いをしていきたいと思います。」
意見を出し合う(議論にしていくことが重要)
「○○さんの意見に付け足して・・・」
「△△さんとは反対に・・・」
など、一方通行の発言にならないようにしていきましょう。司会者は、発言を促したり、「○○という意見が出ましたが、Aさんはどのように考えますか?」など議論が展開していくような働きかけをします。
出た意見をまとめる
司会者は、出た意見を簡潔にまとめ、このカンファレンスで学び得たことや、至った結論を発表し締めの言葉をいう。
学校や実習先の方針により異なる部分があるかもしれませんが、基本的にはこの流れで進行することが多いです。
私の失敗談
私が学生の頃のカンファレンスは、本当に“発表会”そのものでした。
メンバーが1人ずつ意見を発表し終えた後、誰も何も言えずに沈黙。「なんて発言しよう・・・」とただただ焦り、他のメンバーもうつむいていました。場の空気も重くなり、指導者さんからは「このカンファレンス、意味あった?」と一言。悔しい、情けない、何とも言えない気持ちになったのを今でも覚えています。
当時はカンファレンスにとても苦手意識があり、毎日憂鬱でした。今振り返ってみると、「何か発言しなきゃ」ということで頭がいっぱいで、カンファレンスの本当の目的を理解しておらず、事前準備も足りていなかったなと反省しています。
まとめ
カンファレンスに苦手意識がある学生さんは本当に多いと思います。実際に私もそうでした。ですが、カンファレンスを何のために行うのかを考え、事前準備をして臨めば学びの多いものになります。
実際に、学生さんが十分に準備をしてカンファレンスに臨み、活発に議論が展開されている姿を見ると、「この学生さんたちの前向きな姿勢素敵だな」とチーム全体の印象が良くなります。
慣れるまでは、テーマを決めたり、目的を考えたり、事前準備をしたりと大変に感じるかもしれません。でもここで頑張れた学生さんには、本当にたくさんの学びがありますよ。
今後もこのブログでは頑張る学生さんの背中をそっといしていけたらと思っています🌸
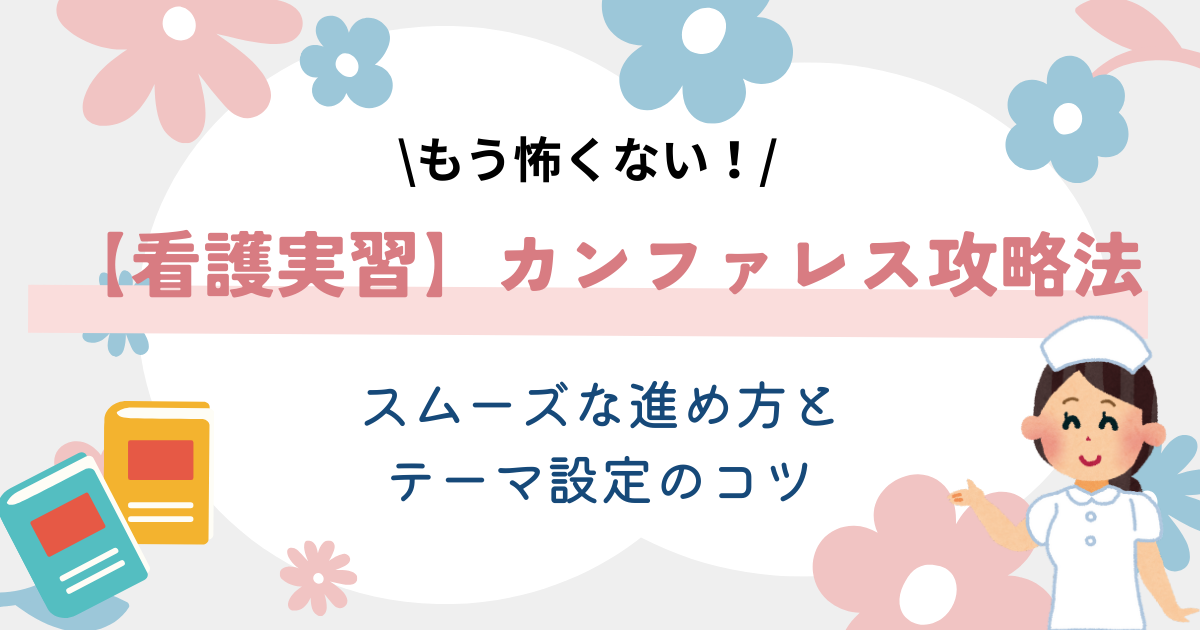
コメント